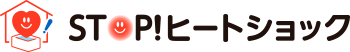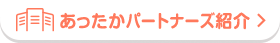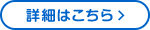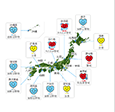プカ太郎:内科医である今村先生が「健康と住まいの関連」について着目されたきっかけを教えてください。
今村先生:私は長年、日本医師会で仕事をしており、その中で最初に担当したのが環境保健でした。環境保健とは環境が人間の健康に及ぼす影響を明らかにし、その対策を講じる学問です。中でも特に住環境の問題に関心を持つようになったのは、いわゆる「シックハウス症候群」がきっかけでした。
プカ太郎:「シックハウス症候群」って、建物の建材などに使用されている化学物質などが原因で、健康に様々な悪影響をもたらす症状ですね。
今村先生:そうです。私が日本医師会で仕事をはじめた当時はまだ「シックハウス」という言葉は一般的ではありませんでした。
プカ太郎:ふむふむ。
今村先生:日本医師会の環境保健担当だった私は「シックハウス症候群」に関するシンポジウムなどに招かれたり、自分で勉強したりするうちに「住環境の問題は健康と密接に関わっている」ことに気付いていきました。
プカ太郎:なるほど!
今村先生:それまでは、住環境の問題は建築関係者の分野という認識が強かったのですが、知れば知るほど住環境や住まい方が健康に与える影響は非常に大きいことが分かり「医療関係者もこの問題に関心を持つべき」だと強く感じるようになりました。
プカ太郎:住まいと健康の関連性は、今でも一般的に知られていないので、当時はもっと知られていなかったのでしょうね。
今村先生:そうですね。しかし近年になって、住環境が健康に与える影響についての研究が進み、科学的根拠(エビデンス)も明確になってきています。ですので、患者さんの診療を行うだけでなく、その方がどのような住環境で生活しているのかを考えることが、健康維持にとって非常に重要であると分かってきました。
プカ太郎:現在では、多くのお医者さんがこの事実を知っているのでしょうか?
今村先生:漠然と「住環境が健康に影響を与える」ということ自体は、多くの医師が理解しているでしょう。ただし、具体的にどのような影響があるのか、例えば「血圧にどの程度影響するのか?」「夜間の排尿回数にどう関係するのか?」「家の中での転倒リスクが室温によってどれほど変わるのか?」といった詳細なデータについては、まだ十分に知られていません。
プカ太郎:詳しい情報はまだまだ認知されていないのですね。
今村先生:2014年から国土交通省の予算で全国調査が行われ、さまざまなデータが明らかになってきました。その結果、室温が健康に与える影響は予想以上に大きいことが分かってきています。現在は、その知見を医療者にも広く伝えるため、さまざまな媒体を活用して発信している段階です。

プカ太郎:お医者さんって、病院で患者さんを診察しているイメージが強いですが、今村先生は患者さんのご自宅に伺っての診察もしているのでしょうか?
今村先生:はい。約30年前から訪問診療も行っています。以前は訪問診療の患者さんが40人以上いましたが、現在は年齢を重ねたこともあり、診ている患者さんの数は少なくなりました。それでも住環境の重要性を考え、患者さんに「室温管理を工夫すると良いですよ」といったアドバイスを行うことがあります。実際に、NHKの「クローズアップ現代」でも、私の訪問診療の様子が取り上げられたことがあります。
プカ太郎:訪問診療を続ける中で、患者さんのお住まいを見て、気付いたことなどがあれば教えてください。
今村先生:患者さんの住環境は本当に様々です。比較的経済的に余裕がある方は、自分で工夫し、快適な住環境を整えておられることが多いです。しかし、経済的な事情から住環境に十分な投資ができない方や、築年数が古い住宅に住んでいる方は、冬は非常に寒く、夏は極端に暑い環境で生活されていることが多いです。
プカ太郎:冬は特にヒートショックが心配ですよね。だんだんヒートショックの存在も周知されてきていますが、ヒートショックに関して心配している点や気をつけた方が良い点はありますか?
今村先生:おっしゃる通り、ヒートショックの存在は以前より多くの人が知るようになりました。しかし、ヒートショックについて語る際に「温度差が大きいほど危険」と言われることが多いですが、私は必ずしも温度差だけが問題ではないと考えています。
プカ太郎:そうなんですか!?
今村先生:例えば、北海道の住宅では、室内の温度が24度程度に保たれており、外に出ると0度以下のこともあります。これだけの温度差があるにもかかわらず、冬場の死亡率は北海道の方が低いのです。もし「温度差がヒートショックの原因」という単純な理屈であれば、北海道の人は外に出るたびに倒れてしまうはずですが、実際にはそうではありません。
プカ太郎:たしかに!
今村先生:私が考えるに、北海道はそもそもの住宅環境が良いために、そもそも住民の健康状態が良いのではないかと思います。
プカ太郎:北海道の家の中はすごく暖かいと聞きますね。
今村先生:そう。北海道の住宅は断熱性能が高く、室温が安定しています。そのため、常に体の状態が良いのです。一方で、もともと寒い住まいに長時間いる方は、体が冷えた状態のまま外に出るため、急な温度変化に耐えられずヒートショックを起こしやすいのではないかと考えています。
この仮説はまだ科学的に完全に証明されたわけではありませんが、少なくともデータとして「寒冷地の方が冬の死亡率が低い」という事実はあります。
プカ太郎:つまり「温度差をつくらないこと」以前に「普段から体を良い状態に整えておくこと」が重要ということですね?
今村先生:その通りです。日頃から適切な室温を保ち、健康的な住環境を作ることが重要なのです。
また、ヒートショック対策として「トイレや浴室を温める」というのはもちろん有効ですが、それだけでなく、住まい全体の温度を均一にすることが理想的です。
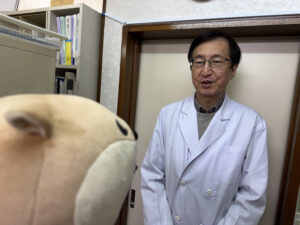
プカ太郎:その他に家が寒いことで特に影響を受けやすい疾患や健康リスクには、どのようなものがあるのでしょうか?
今村先生:冬場の寒さは、特に循環器系の疾患に影響を与えます。寒さによって血圧が上がりやすくなるだけでなく、血管が収縮してしまうため、脳梗塞や脳出血、心筋梗塞といった疾患のリスクが高まります。
プカ太郎:知らなかった!
今村先生:また、呼吸器系の疾患にも影響を及ぼします。低温になると免疫力が低下し、肺炎を発症しやすくなります。冬場にインフルエンザなどの感染症が増えるのも、気温の低下によって粘膜の抵抗力が落ち、体が消耗しやすくなることが一因です。
プカ太郎:なるほど!
今村先生:寒い住環境で生活されている方の場合、夏の間は血圧が安定しているのに、冬になると急激に血圧が上昇することがあります。しかし、住環境をすぐに変えることは難しいため、冬の間だけ血圧の薬を増量するといった対応を取ることもあります。
プカ太郎:薬が増えることもあるのですね。
今村先生:春や秋のように室温が24~26度程度であれば、特別な努力をしなくても体温調節が自然に行われるため、体にとって負担が少なく、快適に過ごせるのです。こうした理由からも、適切な室温を保つことが健康維持のために非常に重要だと言えます。
プカ太郎:先生は実際に患者さんにどんなアドバイスを行っているのですか?
今村先生:冬になると人間の体は気温の影響を大きく受けます。寒い環境では血管が収縮し、血圧が上昇する傾向があります。そのため「お住まいの室温が必要以上に低くなっていませんか?」と患者さんに確認しています。実際に、血圧を測っている患者さんの中には「家の室温はだいたい15度くらいです」とおっしゃる方もいます。そういう場合には「それは少し寒すぎますね。もう少し暖かくした方が健康に良いですよ」とアドバイスすることができます。
プカ太郎:このように教えてもらわないと、家の温度ってそこまで意識しないかもしれないですね。
今村先生:また、訪問診療を行っているご家庭では、実際に室温を確認することもできます。温度だけでなく、湿度や照明の明るさなど、さまざまな住環境の要素が健康に影響します。例えば「もう少し窓際の寒さを防ぐ工夫をすると良いですね」といったアドバイスをすることもできますし、ご家族に対して「この環境を改善すると、健康に良い影響がありますよ」と指導することもあります。
プカ太郎:お医者さんが言ってくれると「対策しよう」という気持ちになりそうですね。
今村先生:家の中は暖かくても、廊下やトイレが冷えているケースもあります。例えば、おばあちゃんが裸足で冷たい廊下を歩いてトイレに行くことがある場合「廊下を歩くときは靴下を履くようにしましょう」といった助言ができます。ただし、スリッパを履くと転倒しやすい方もいるので、その場合は「スリッパではなく、滑りにくい靴下を履くのが良いですよ」といった具体的なアドバイスをすることが大切です。
プカ太郎:お医者さんに家の環境のことまで気遣ってもらえるなんて嬉しいですね。
今村先生:住環境に関するアドバイスができる医師が増えることは、患者さんの健康を守る上でとても重要だと考えています。
後編に続く

●後編はこちらからチェック!
⇒【後編】内科医に聞く、住まいと健康の密接な関係
●ヒートショックのメカニズムをご存じですか?詳しく知りたい方はこちらもチェック!
⇒ヒートショックのメカニズム
●冬場の温度差には要注意。詳しく知りたい方はこちらもチェック!
⇒ヒートショックの死亡数
●症状を学んでしっかり対策しましょう!詳しく知りたい方はこちらもチェック!
⇒ヒートショックによる症状について