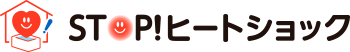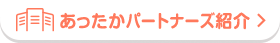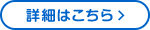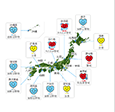~前編からの続き~
プカ太郎:今村先生のこれまでのご活動の中で、特に印象に残った出来事があれば教えてください。
今村先生:取り組みの中で印象に残ったことというよりも、政策の変化が印象深かったですね。以前、厚生労働省は「住環境と健康の関係についてエビデンス(科学的根拠)がない」として、国の予算を使って対策を講じることには慎重でした。しかし、2014年から国土交通省が実施した調査によって、非常に精度の高いデータが得られました。
プカ太郎:「住まいと健康の関係」について、国が認識するようになったのは、たったの10年ほど前からなんですね。
今村先生:そうなんです。日本ではまだまだ研究や調査が始まってからの歴史が浅いのです。しかし、イギリスでは早い段階で「高齢者は18度以下の住環境で生活させてはいけない」という法律が制定されています。
プカ太郎:イギリスではなぜ早くから制度が整っていたのでしょうか?
今村先生:ナイチンゲールという偉人をご存知ですか?
プカ太郎:はい。クリミア戦争で活躍した、イギリスの著名な看護師ですね。絵本で読んだことがあります!
今村先生:そうです。ナイチンゲールは「健康は住まいと住まい方で決まる」と述べているんです。彼女の時代には、科学的なデータに基づくエビデンスはありませんでしたが、患者を看護する中で「住環境が健康に大きく影響する」ということを経験的に理解していたのです。
プカ太郎:ナイチンゲールは現場の経験で、住環境と健康の関係を知っていたのですね!
今村先生:そうですね。こうした背景もあってイギリスでは古くから住宅環境に対する意識が高く、現在も住宅政策に力を入れています。「室温18度以上を維持することが重要だ」というルールも、その歴史的背景が影響しているのです。
プカ太郎:そうだったんだ!
今村先生:ちなみに世界保健機関(WHO)も「1年を通して室温を18度以上に保つことが健康維持のために重要である」と強く勧告しています。

プカ太郎:日本が知らないだけで、国際的には知られていることなんですね!なぜ日本では住環境と健康の関係は知られていないのでしょうか?
今村先生:日本の住宅は、長らく「夏の暑さをどうしのぐか」に重点を置いて設計されてきました。その背景には「冬は厚着をすればしのげる」という考え方があります。
プカ太郎:ほうほう。
今村先生:平安時代の貴族の屋敷を思い浮かべてください。大きな開口部があり、風通しの良い構造になっていました。冬場は室内が非常に寒くなりますが、障子や布を使って寒さをしのいでいました。このように、日本では伝統的に「寒さは耐えるもの」という価値観が根付いていたのです。
プカ太郎:たしかに。わかる気がします。国によって住まいに対する考え方や背景が全然違うのですね。
今村先生:その通りです。こうした違いは、それぞれの国の気候や建築文化によるものですが、日本もそろそろ「健康やエネルギー効率を考えた住宅設計」にシフトしていくべきではないかと感じています。
プカ太郎:日本はまだまだ健康的な住環境に関しては後進国なんですね。
今村先生:日本の住宅の断熱基準を世界と比較すると、かなり低いレベルにあります。特に、既存の木造住宅の断熱性能は、先進国の中でも最低レベルとされています。
プカ太郎:最低レベル!?
今村先生:はい。新しく建設されるマンションなどは最新の基準を満たしていますが、既存の木造住宅の断熱性能は非常に低く、その影響で冬場の健康リスクが高まっています。特に、日本の住宅ではアルミサッシが多く使われていますよね?
プカ太郎:アルミサッシ!古いお家ではよく見ますね。
今村先生:アルミという素材は熱伝導率が非常に高いのです。そのため
・夏場は外の熱が直接伝わり、室温が上昇する
・冬場は外の冷気がダイレクトに伝わり、室内の暖気が逃げてしまう
という問題が発生します。実際に日本の住宅では、熱のロスの約7割が窓枠から発生しているとも言われています。
プカ太郎:約7割も!?
今村先生:はい。海外では、すでに窓枠に樹脂を使用したサッシが主流になっています。日本でも、最近の住宅では樹脂サッシや、アルミと樹脂を組み合わせたサッシが採用されるようになっています。
プカ太郎:日本でも新しい住宅は、きちんと断熱性が担保されているのですね。なぜ、新しい住宅は断熱性が担保されるようになったのですか?
今村先生:近年になって「住環境と健康」に関する科学的なエビデンスがしっかりと示されたことが大きいですね。日本では、これまで住環境と健康の関係についての関心が比較的低かったのですが、イギリスをはじめとする国々のデータや、日本での調査結果が国際的にも評価されるようになり、日本の政策にも影響を与えました。
プカ太郎:へー!
今村先生:それに加えて、国会議員の方々の理解が深まったことも影響しています。この問題の重要性を認識した議員の方々が「健康・省エネ住宅を推進する議員連盟」を立ち上げました。この議員連盟ができたことで、国会でも住環境と健康の関係についての議論が進み、政策に反映されるようになりました。国会でこうしたテーマが取り上げられると、厚生労働省や国土交通省といった官庁も動きやすくなるのです。
プカ太郎:なるほど〜。
今村先生:厚生労働省は、国民の健康政策として「健康日本21」という指針を数年ごとに策定していますが、最近の改定では「適切な室温を確保することの重要性」が盛り込まれるようになりました。また、厚労省の公式ホームページにも「室温管理の重要性」についてのページが作成されました。
こうした政策の変化は、私自身も非常に印象深いですね。以前は住環境と健康の関連についてなかなか理解が得られませんでしたが、今では国の機関もその重要性を認識し、対策が進められつつあります。
プカ太郎:日本の住環境もだんだん良くなってきてるんですね。
今村先生:そうですね。今では様々な省庁で断熱改修に関する補助金※も充実してきています。
プカ太郎:詳しく教えてください!
今村先生:例えば・・・
・窓枠の改修 → 経済産業省の予算
・住宅全体の断熱改修 → 国土交通省の予算
・省エネルギー対策 → 環境省の予算
といったように、多くの支援策があります。
また、自治体からも断熱改修のための補助金が出ることもあります。
プカ太郎:知らなかった!
今村先生:そうなんです。こうした補助金があることって一般的にほとんど知られていないんですよ。
プカ太郎:たしかに。
今村先生:多くの人は「住宅改修には莫大な費用がかかる」と思い込んでしまい、そもそも検討すらしない方が大半です。
プカ太郎:そうなっちゃいますよね。
今村先生:しかし、近年では国や自治体が費用を補助する仕組みが用意されています。それを上手に活用すれば金銭的な負担をかなり減らせるケースもあります。こちらは自治体によっても異なるため、まずはお住まいの地域の自治体に問い合わせてください。
プカ太郎:費用の補助も色々と用意されているんですねー。知らなかった!
今村先生:実際に北海道の礼文島で断熱改修を行った事例では、暖房灯油使用量が、改修前2023年1,2月で440リットルだったものが、改修後の2024年1,2月で210リットルまで削減されました。その後はずっと光熱費の負担が軽減されるわけです。
プカ太郎:お得どころか元が取れるケースもあるんですね!
今村先生:はい。また、健康とは違うメリットですが、断熱改修をするとエネルギーの浪費が少なくなるため、二酸化炭素の排出量削減にも貢献できます。

プカ太郎:今村先生が考える「健康的な理想の住宅」はどんな住まいでしょうか?
今村先生:今の時代、DX(デジタルトランスフォーメーション)の概念が広がっていますので、ITやIoTをうまく活用した住宅が理想的だと考えています。
プカ太郎:ほうほう。
今村先生:例えば、エアコンメーカーでは赤外線センサーを利用して、室内の温度ムラを測定する技術がすでに開発されています。こうした技術を応用すれば、自動で最適な温度に調整するシステムを導入することが可能です。現在はリモコンで操作するのが一般的ですが、今後はAIを活用して自動的に風量や風向きを調整するエアコンが普及するでしょう。
プカ太郎:ハイテク!
今村先生:また、高齢者の一人暮らしが増えている中で、遠方に住むご家族が「おばあちゃんの部屋が暑すぎないか、寒すぎないか」と心配することも多いです。高齢者の方の中には「エアコンの操作方法が分からない」とおっしゃる方もいらっしゃいます。そのため、ウェアラブル端末を活用して、血圧や脈拍、室温などをリアルタイムでモニタリングできるシステムがあれば、ご家族が遠隔でエアコンを操作することも可能になります。
プカ太郎:現代技術を駆使すれば離れて過ごす家族までカバーできるんですね!
今村先生:はい。こうした「スマートハウス」の概念が広がることで、高齢者が安心して暮らせる環境が整うのではないかと思います。
プカ太郎:住まいを断熱改修する場合、どんなタイミングで行うのが理想的ですか?
今村先生:もちろん皆さんライフスタイルやライフステージはそれぞれ違うと思うので、一概には言えませんが、私がオススメしたいタイミングは定年退職の時ですね。
プカ太郎:なぜでしょうか?
今村先生:退職したばかりのタイミングで住宅の改修を行えば、その後の健康を維持しやすくなります。65歳を過ぎると、徐々にさまざまな病気のリスクが高まります。その前に、健康を維持しやすい住環境を整えることが重要です。だから65歳前後の方が退職金の一部を活用して、これからの10〜15年を快適に暮らせる住環境を整えれば、資金的にも年齢的にもちょうど良いタイミングだと考えています。
プカ太郎:納得です!
今村先生:ちなみに補助金制度を活用すれば、自己負担を抑えながら住宅を改修することも可能です。住宅を新築する必要はなく、補助金を活用して窓の断熱性を高める、床暖房を導入するなど、小規模な改修でも大きな効果が得られます。
プカ太郎:今後、日本で「健康的な暖かい住まい」が普及していくためには、どんなことが必要だと思いますか?
今村先生:まずは「住環境と健康」は密接なつながりがあるという事実をより多くの医療関係者に知ってもらうことでしょうか。そのために私たちは全国の各都市でシンポジウムを開催し、啓蒙活動を行っています。
プカ太郎:他にはありますか?
今村先生:建築業界と医療業界、それぞれの団体が縦割り構造になってしまっているので、もっと横の連携が取れるようになると良いなと思います。例えば、自治体の首長が「この地域では、国や自治体の補助金を活用して、住民に対して断熱改修を推進する」と決定し、その際に健康部門と建築部門が協力して取り組むよう指示を出すことが必要になってくると思います。
プカ太郎:なかなか難しそうですね。
今村先生:そうですね。実現するためには「住環境が健康にどれほど影響を与えるか」を示す具体的なデータをさらに集め、発信することが重要だと考えています。
例えば・・・
・断熱改修を行った後に血圧がどれだけ改善されたか?
・断熱改修の3年後の血液検査データがどう変化したか?
・断熱改修後に住人の睡眠の質がどれほど向上したか?
といったデータを蓄積し、可視化して示すことで、住民の皆さんが「それならうちもやろう」と思えるようになるのではないかと思います。
プカ太郎:なるほど。まだまだデータを集めて発信・啓蒙していくことが大切なんですね。今村先生、本日は貴重なお話を聞かせていただきありがとうございました!
※補助金については、製品や自治体によって補助条件等はまちまちですので、補助内容の詳細はリフォーム業者やお住まいの自治体にお問い合わせください。

●前編をまだチェックされていない方は前編からチェック!
⇒【前編】 内科医に聞く、住まいと健康の密接な関係
●ヒートショックのメカニズムをご存じですか?詳しく知りたい方はこちらもチェック!
⇒ヒートショックのメカニズム
●冬場の温度差には要注意。詳しく知りたい方はこちらもチェック!
⇒ヒートショックの死亡数
●症状を学んでしっかり対策しましょう!詳しく知りたい方はこちらもチェック!
⇒ヒートショックによる症状について