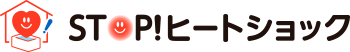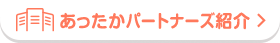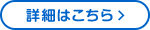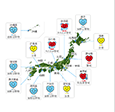初の試み!ライフバルで「STOP!ヒートショック」研修会を開催!
プカ太郎:今シーズンは販売店(東京ガスライフバル)向けの活動に「STOP!ヒートショック」プロジェクトを活用されたと伺いました。
椎名さん:はい。各ライフバル向けに営業支援を行っている部署による定期的な研修会の一つとして、「STOP!ヒートショック」プロジェクトの協力のもと、勉強会を開催しました。初の試みです。

プカ太郎:研修会に参加されたのはどのような業務を行う方だったのでしょうか?
椎名さん:ライフバルの点検・営業・メンテナンス業務担当者を対象としていて、皆さん普段からお客様との接点を多く持つ方々です。
プカ太郎:ぼくのおうちに点検に来る方も参加していたのかなー。そもそも、どのようなきっかけで勉強会を行うことになったのですか?
椎名さん:ヒートショックに関するメディアでの露出も増え、お客様との接点の中でヒートショックに関するお話をする機会も増えました。特に、気温が下がってくる時期はヒートショックに気を付ける時期でもあり、その時期は販売店業務の繁忙時期にもなりますので、ほかの時期よりお客様に商品のご案内をする機会が自然と多くなり、お客様からヒートショックに関してのご質問を受けることもあります。その際に正しい知識を持って商品をお勧めし、アドバイスすることを目標に開催することになりました。
プカ太郎:やはり、お客様側もヒートショックへの関心が高まっているんですね。
椎名さん:そう感じますね。
プカ太郎:勉強会はどのような内容だったのでしょうか。また、勉強会後のライフバルさんの変化など何かありましたでしょうか?
椎名さん:「STOP!ヒートショック」担当者を講師として招き、ヒートショックに関する正しい情報やお客様へ説明する際の注意事項、入浴時の7つのポイントのレクチャー、対策おすすめ商品紹介などを行いました。勉強会を実施したライフバルはその後、お客様にご案内する際、入浴時の7つのポイントを説明するために「STOP!ヒートショック」プロジェクトが作成したチラシや各協賛メーカー様に作成にご協力いただいた販促チラシを活用していますし、浴室暖房装置や温水洗浄便座を中心に紹介するヒートショック対策チラシを独自に作成し、お客様に提案しています。
プカ太郎:プロジェクトコンテンツの活用で日頃のご提案に幅が生まれた感じですね。
椎名さん:はい。今後は、ヒートショックが起こりやすいイメージの強い浴室にとどまらず、おうち全体のヒートショック対策にも話が広がり、床暖房をはじめとしたガス機器関連や断熱などのリフォームについてのお話も今後は増えるのではないかと思っています。
「連携の強化」でより一層の啓発

プカ太郎:今シーズン、東京ガスグループさんは「STOP!ヒートショック」プロジェクトの幹事企業として様々な連携を模索されたそうですね。実際にはプロジェクトとしてどんな連携が行われたのでしょうか。
五十嵐さん:はい、まず、各地の消防局との連携ですが、東京ガスの各支店や企画部から各消防局へアプローチし、STOP!ヒートショックのチラシやポスターの掲示の他、消防署の表側にあるサイネージにヒートショックへの注意喚起を行う画像を投影いただきました。
プカ太郎:消防さん関連は注目も集まったのではないでしょうか。
五十嵐さん:そうですね。消防関連の大きなイベントである1月6日の東京消防出初式では、チラシ配布と一緒に、来場されたご家族連れやお子様にプカ太郎シールを500枚配布し、大変好評でした。
プカ太郎:ぼくも当日行きましたがブースがとても盛り上がっていましたね!ヒートショックの資料やぼくのシールもお子様へ「じいじやばあばにお話ししてね」と伝えながらお渡しするなどの工夫がされていて、意外な接点が生まれているなと思いましたよ。
五十嵐さん:さらに、医療機関との連携も強化しました。プロジェクトには協力医療団体がいくつかありますが、その中の東京内科医会主催の市民セミナーでは、東京ガスリノベーションから「住まいの環境を整える住宅リフォーム事例」をご紹介したり、東京都病院機構にアプローチして、都立病院にポスターを掲示していただいたり、チラシ配布をお願いしたりもしました。
また、当社とお取引いただいている機器メーカー様や所属している業界団体様にプロジェクトの参加を呼びかけ、ご賛同いただくことで協賛企業や協力団体を充実させることができました。
プカ太郎:各企業様・団体様にも盛り上げていただいていますよね。各方面の様々な企業さんや団体さんと連携を図ることで、プロジェクトにどのような効果が生まれていると思われますか?
五十嵐さん:市民の皆様がヒートショック対策を理解したうえでアクションを起こしていただくには、個々の企業だけの活動では力不足であり、みんなで力を合わせて連携することが重要です。有志の協賛企業が結集し、プロジェクトからの発信をみんなが活用することで相乗効果が生まれ、ヒートショックの認知度や対策の実施率が向上してきたのだと考えます。
7年にわたるSTOP!ヒートショックの活動をこれからも盛り上げていくことが、ヒートショック対策の実行を一般化させ、安心して暮らせる住まいが増えることに繋がると確信しています。
プカ太郎:いろいろ広がりますね。今後も様々な分野の皆さんと協力していきたいですね。
エネルギー企業としてのヒートショック対策に対する思い
プカ太郎:東京ガスグループさんは、エネルギー企業として、ヒートショック対策と常に近いところにいらっしゃるのではないかと思いますが、ヒートショック対策に対する思いなどをお伺いできればと思います。
五十嵐さん:東京ガスの設立以来140年にわたり、グループ全体でお客さまの暮らしを安心で豊かにするための活動を継続してまいりました。ところが近年、最も安心できるはずの自宅の中でのヒートショックによる被害が多数報告されるようになり、その解決のために「STOP!ヒートショック」プロジェクトに参加いたしました。市民の皆様と多くの接点を有する東京ガスグループは、これからも「STOP!ヒートショック」活動を通じ、ヒートショックへの不安と被害を解消するための情報発信に努めてまいります。
プカ太郎:ありがとうございます!より多くの方々に正しく役立つ情報を届けていきたいですね。

今後の「STOP!ヒートショック」プロジェクトの活動によせて
プカ太郎:今後、このプロジェクトを通じて実現したいことはありますか?
五十嵐さん:ヒートショック対策は「今日からできること」から「リフォームなどを通じて実現できること」まで複数の選択肢があります。まずは当社のお客様がヒートショックの被害に遭わないため、適切な情報発信を展開したいと考えます。
また、ヒートショック対策と暮らし向上を同時に実現させる商品や設備のご提案も積極的に行ってまいります。例えば、内窓の設置や断熱層の強化などはヒートショック対策と省エネルギー効果の両立が期待できますし、古いタイプの寒い浴室を断熱性の高いシステムバスに交換しミストサウナを設置すると、浴槽浴と同等の満足感が得られ、将来にわたり入浴時の事故防止が期待できます。
東京ガスグループはヒートショック対策を通じ、安心・安全に暮らすことのできる住まいの普及を目指してまいります。
プカ太郎:より快適に過ごせる住宅設備のご提案などこれからますます期待したいですね!
今日はありがとうございました。

●ヒートショックのメカニズムをご存じですか?詳しく知りたい方はこちらもチェック!
⇒ヒートショックのメカニズム
●冬場の温度差には要注意。詳しく知りたい方はこちらもチェック!
⇒ヒートショックの死亡数
●症状を学んでしっかり対策しましょう!詳しく知りたい方はこちらもチェック!
⇒ヒートショックによる症状について
●そのほかのインタビューもぜひチェックしてください!読んでみたい方はこちらもチェック!
⇒横浜市が推進する住まいの「STOP!ヒートショック」